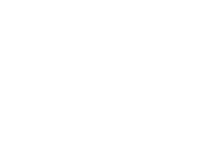自分を生きた人―伊藤勉黄
伊藤勉黄は、一冊の手作りの和紙帳を残しています。表紙には見慣れた筆跡で「勉而一」。荘子の人間世篇に出てくる言葉で「つとめていつ」と読みます。おそらく「勉」の文字もあって、タイトルに使ったのでしょう。伊藤勉黄はその和紙帳について書いています。
「勉而一=勉強して専一になることと題した手作りの和紙帳が、わたしの机上に置いてある。日常の所感を思いつくままに、断片的ながらノートするのだが、筆ペンの墨は和紙に浸透して、その時々の記憶をよみがえらせてくれる。じっくり考えることによって、自らを律して制作への糧になればいいのだと思う」。
「勉而一」を、自らの決心に引き寄せて解釈していたことがわかります。そして所感のいくつかを抜き書きしています。その中から三つ紹介します。
「制作方法に馴らされることを戒め、自らのこころに問いかける姿勢こそ大切なり」。
「自ら自分に頼れる人間にこころを育成すること、思索は生きている証左、そして制作と表裏一体であろう」。
「成るように成る、成らせるように成る。成り行きまかせで生きてきた。成り行きは成るように生きるという ことだが、成るように成るために、自らを律し、自分の信念で生きてこそ人生体験となって、こころに蓄積された 作品があるといえようか」。
1981年 豊穣の女神達(45 x 75)
「成るように成る」―伊藤勉黄は、その言葉を口にするにふさわしい人でした。とくに還暦を経て、そのことの自分自身への確信が生まれたように思われます。しかしそれは老成を意味しません。自作年譜1977年に「画名を勉黄とする。還暦を過ぎて、晩成を約束のこころとして、黄の一字を加えた。頼れるのは自分自身であるから─これからが本物の仕事と力んでみる」とあります。「力んでみる」に老成とはなじまない伊藤勉黄の終生の資質、若気を感じます。
1978年に「伊藤勉黄30年の歩み展」(静岡松坂屋)を開きます。1980年からは、東京銀座「ギャラリーねこ」で新作による個展を毎年開催します。勉黄になってからの仕事ぶりは猛烈というほどの印象を私たちに与えました。豊潤な作品を次々に生み出します。その一端は、1982年の2人展(池田20世紀美術館)で貴婦人シリーズ「豊饒の女神たち」連作となって発表されます。
1983年 花摘み(1)(45 x 75) 1988年 風媒花 (84 x 75)
その後の主な作品を国展で追うなら「花摘み」「旅愁・花々の挿話」「花の肖像」「花信風」「風媒花」「花日記」と花にちなんだタイトルの作品が続きます。人と花とは、伊藤勉黄にとって永遠のモチーフでした。国展での最後の発表作も「花遊園」(第65回展1991年)。花園に遊ぶ少女たち。胸に重なる十字の形は、少女たちが思い悩んで、ふと立ち止まる十字路に見えます。道は交差し合うと、彼方へ消えて行きます。求めて止まない作者の思いが自ずと形になってしまった作品、「成るように成って」しまった作品に思えます。
これら勉黄作品に羨望を覚えるのは、老いの気配がいささかもないことです。「花遊園」に至るどの作品にも、若々しい清新な気が満ちています。そして、思いと一体化した闊達な刀さばき、油性絵の具による独自な摺り、豊かで重厚な色彩、それが伊藤勉黄の世界です。1992年75歳で亡くなるその病床で、最後まで 構想の筆をとっていました。
 私たちはともすれば己を失い、皮相なものに流れがちです。そんな時、伊藤勉黄を貫き通した伊藤勉黄の仕事は、いよいよ深い存在感で私たちの前に立ち現れます。
私たちはともすれば己を失い、皮相なものに流れがちです。そんな時、伊藤勉黄を貫き通した伊藤勉黄の仕事は、いよいよ深い存在感で私たちの前に立ち現れます。
1991年 花遊園 (48 x 75)
(投稿者)青木鐵夫 版画部会員