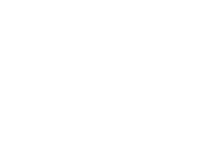絵画部 会員インタビュー
第2回 沖縄 2003
北海道~沖縄までの会員・準会員のインタビューとご紹介
「国画会絵画部沖縄地区の現況」
沖縄出身の絵画部会員および準会員は、安次富長昭会員、金城規克会員、それに永山信春準会員の3名である。永山準会員は、3年前に茨城県に転居したので、現在のところ県内在住者は会員2名のみである。以前は準会員も3名いたが、国展への出品が続かなくなり、2名は10年程前に退会した。
沖縄県は国内で唯一陸路で継がっていない県である。県外の展覧会への出品は、殆んど航空貨物での搬入、搬出となるので、その費用は他県に較べると負担が大きい。県内には新聞社主催の「沖展」というのがあって、それに出品している絵画人口はかなり多い。今年で55年になるが、しかしその絵画部への出品者が国展のみならず、県外の公募展に出品しているのは非常に少ない。作品が比較的運搬し易い工芸部出品者は県外の展覧会への出品も多く、国展の会員、準会員も数多い。その中には人間国宝も含まれている。
沖縄県の亜熱帯や島嶼性という自然条件。首里王府時代に築きあげられ、今日に受け継がれてきている伝統文化。それらの特性を発揮する作家が絵画部にも輩出することを期待したい。
(文 安次富長昭会員)
![]()
安次富長昭会員
1959年(昭34)冬のある日、国画会会員で沖縄の大先輩画家、南風原朝光先生に道で偶然お会いした。一緒にそばを食べようということになり、そば屋に入ってそこでの話。君は沖縄だけで絵を描いているだけでは大した絵かきにはなれないよ。広い世界に出て人にもまれなければならない。東京の公募展にも出品してごらんなさい。と、ご忠告を受けた。しかし当時の沖縄は米国統治時代で、本土の情報も少く、東京にどういう展覧会があるのかも知らなかった。そこで、取りあえず南風原先生が出品している国展に出してみようということになり、それが国展にかかわるきっかけとなった。 当時は、東京に行くにもパスポートが必要で、船と汽車を乗りついで5日もかかった。
初めの頃は、100号の絵を枠からはずし、5枚ほど重ねて巻き、その梱包を担いで上京したものである。都美術館の地下で荷を解き、枠に張り額縁をつけて1点1点搬入受付まで運んでいった。今考えると、長い旅行のあと引き続きこの作業をやらねばならないのだから、大変なことであった。
1972年(昭47)沖縄は本土に復帰し、私は会員となった。渡航にパスポートの必要もなくなり、作品もそのままアトリエから国展まで航空貨物で送れるようになったのだから、こんな嬉しいことはなかった。
今日までに国展で得たものといえば、苦労した前述の体験や多くの人びととの出会いである。中でも印象に残るのは、初入選したときの国展懇親会場で、たまたま偶然向かい合って座った方が岸田麗子さんで、琉球(沖縄)のことを訪ねられ、また私も「麗子像」の頃の話を聞いたことである。その翌年は小泉清さん(小泉八雲の次男)にお会いし、中野の居酒屋までお供したことなど、まるで、遠い昔のことと思っていた歴史が目の前にあるような気がして、国画会が不思議な人との出会いの場所として思われ、強いカルチュア・ショックを受けたものである。国画会が作品を通して人と人との出会いの場であり、それによって自己を深めることのできる会としての良い伝統を受け継いでいきたいと私は希っている。
![]()
「辺境」 永山信春 準会員
新聞も、テレビも、この頃、沖縄のことがよく話題になる。長寿県にしろ健康食にしろ、海の美しさにしろそれは、大変結構なことだ。しかし、そこに生まれ育った人たちからすれば必ずしも喜ばしいことだけとは思わなかった。何も基地があるからという意味ではない。創造する人たちにとって、土着とか、風土とかは、単なる自然でしかなかった。それはそこにあるだけだった。それまでは地域主義もなかった。だれもそのよさには気がつかなかった。僕も三年前まではそこに住んでいたことになるから、いやが応でも全てを受けとめなければならない現実があった。そこに生まれ育ったこと、大学を出たこと。
著名な評論家が8ミリ大学と言われたけれど、一学年十名ほどの美術工芸科は、少人数だったが、絵画、彫刻、図案、工芸と一応芸術に必要な基礎的なことを、浅く広く学ぶことが出来た。それが、後に自分の創作に非常に役立つことを知った。現代芸術が複雑になるにつれ、一般的な教養の養成が必要になってくる。アメリカの自由主義的なリベラルな教育システムを導入していたのだろう。所詮、芸術は学校を卒業して一人でするものだから。教官も七名ほどでしたが、皆、それぞれに信念を持ち、教授ではなく芸術家という風格を持っていた。卑近な例だが、梅原龍三郎は「ルノアールによって本当の絵かきらしい絵かきと絵かきの生活を身近に知ることが出来た」のを非常に幸福だったと語っている。僕も、そういう時に、そういう土地で、こういう先生方と出会ったことを幸せに思う。また、誇りに思う。
2020/05/12 絵画部・会員インタビュー|